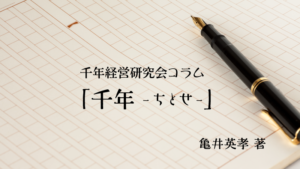No.760 分担
先日、84歳になられる税理士事務所の会長から「相談がある」とメールをいただきました。
創業者である会長は3年前にご子息へ所長の座を譲られ、担当者からはその後の関係も良好だと聴いていましたので、相談内容についてまったく想像ができませんでした。
後日、オンラインでの面談を設定したところ、時候の挨拶の後に出された相談は「生産性を高めたい」というものでした。
事業に直接関わる内容であったので、ご子息と何か揉めて現場への口出しを強めようとされているのではと一瞬不安になりましたが、「息子に頼まれて」と嬉しそうに語る満面の笑顔に、良い関係が継続していることが伺われ、ほっとしました。
とはいえ、内容としては少々理に適っていない印象もありました。既に現場を離れられた方が、生産性向上に直接陣頭指揮を取るというのは、一般的には理解しづらいものです。
しかし、新所長が承継後に取り組まれた新事業が軌道に乗り、他の業務に手が回らなくなってしまっているとのこと。特に主要な経営課題である生産性向上が手つかずの状態となり、今回の依頼となったのだそうです。
面談では、会長が喜々として質問を繰り出され、その回答に真剣に耳を傾けられる姿に、一線を退かれた方の本心を垣間見た気がしました。「やっぱり経営者は生涯現役だな」と。
このような事例は多くはないかもしれませんが、円滑な事業承継を進める上では、引き継いだ者が先代の役割をすべて排除してしまうのではなく、棚卸された経営課題の中から、自ら陣頭指揮を取るべきものと、先代の力を借りることが望ましいものに区分をし、きちんと役割分担をした上でお願いをすることは、とても大切なことだと思います。
一方で、今回の相談については、その後の対応の難しさも感じました。現場担当者の顔が見えてこなかったからです。
経営課題の解決には、その検討プロセスにこそ価値があります。出された結論をただ実行するだけでは、環境や前提が変化した際に、柔軟な対応ができません。
今回の場合、久しぶりに手に入れたおもちゃを独り占めする子供のようなはしゃぎように不安を覚えた私は、「ぜひ引継担当者を決めて、ご一緒に取り組んでくださいね」とお伝えしました。
いずれにしろ、新旧経営者がそれぞれの強みを活かし、経営課題に取り組む姿勢は、理想的な承継の在り方です。ぜひ心に留めておいていただければと思います。