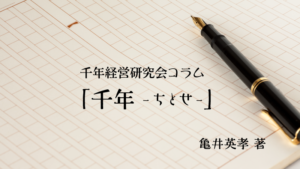No.777 不正
このところ、社員による不正の話を耳にすることが多くなったような気がします。
内容的には、リベートの個人的な受け取りや商品の横流し、経費の水増し請求や架空請求による着服など、その方法はさまざまですが、いかに社内のこととはいえども、犯罪行為であることには違いありません。
もちろん、どこかの銀行の貸金庫からの持ち出しに比べれば、雀の涙ほどの金額ではありますが、それでも犯罪は犯罪。社内でそのような人罪を出してしまった経営者の苦しみ、悲しみ、そして怒りはいかばかりでしょう。
社会的背景から考えれば、物価上昇と、それに見合うだけの収入が増えていないことが理由と考えられそうですが、実際の動機をお聴きすると、ゲーム課金やギャンブル、不倫や夜の享楽がきっかけになっていることが多いとのこと。その理由がまた、社長の悲しみや怒りを増幅させているようです。
しかし、そのような社員を育てたのは当の社長。大いに反省してもらわなければなりません。
もちろん倫理・道徳的に言えば、如何なる不正も許されるものではなく、その責任は、罪を犯した本人に帰することは疑う余地もありません。
ただ、完璧な人間などどこにもいません。必ず心に“すき”を持っているものです。そして、ちょっとした出来心でしてしまったことが、誰にもばれず、何ら変わらない日常が過ぎていくと、「もう一度だけ」「これが最後」と自分に言い訳しながら何度も何度も繰り返す。そしてそのうち、その行為そのものが当たり前になってしまうものなのです。
そのような犯罪者を作ってしまうのは、人間の特性を知らない不勉強な、信頼という言葉を自分に都合のいいように使う、社員への本当の愛が足りない経営者である、との自覚が必要です。
経営者はまず、社員に犯罪を絶対に起こさせないという強い使命感と覚悟を持たなければなりません。
その上で、「自社においては、どのような不正が発生する可能性があるか」「そのような不正を発生させないようにするためにはどのような対策が必要か」を徹底的に検証・研究して、適切な対策を打たなければなりません。
さらに大事なのは、教育です。心から「世のため、人のため」を思って仕事をしている人が、不正など起こしようがありません。仕事に誇りと信念をもってもらうための教育が大切なのです。
そして何より、社員に向ける経営者(ときとして上司)の“愛”が、最好・最強のブレーキとなります。人は、自分を愛してくれている人を裏切ることなどできません。どんなに苦しい状況にあったとしても、ギリギリのところで踏み留まってくれるものなのです。
皆さんもこれを機に、不正防止の「仕組み」と「教育」、そして社員さんに向けている自分の「愛」について、一度振り返りをしていただければと思います。