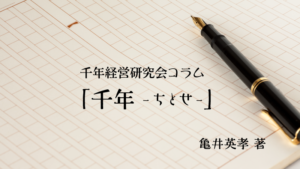No.772 働き方
先日、ある会社の「ビジョン検討会議」なるものにオブザーバー参加させていただきました。
この会議は、経営・管理者層、ベテラン社員層、若手社員層の3階層に分かれて、将来どんな会社にしていきたいかを話し合うことを目的としていました。
各テーブルで活発な意見が交わされていましたが、途中からあることに気が付きました。
将来に対して前向きに大きな夢が語られていたのは経営・管理者層とベテラン社員層で、若手社員層は今の延長線上でできることに終始していました。それどころか、彼らの話題は今の仕事への不満や「できない理由」に偏り、新たなできない理由が出てくるたびに盛り上がるという、会議の主旨とは逆の流れになっていました。
もちろん、できない理由を乗り越えた先に明るい未来が待っている、というのであればよいのですが、その先の光はまったく見えては来ませんでした。
そのことに気づいた私は、再度社長から会議の主旨・目的をお伝えいただきました。しかし、一時的にはビジョンらしい意見も出たものの、後半になると元の木阿弥、またネガティブな話題が中心になってしまいました。
なぜこのようなギャップが生じてしまったのか。終了後に行った社長との面談の中で、その理由が見えてきました。
かつては当社と同じく不夜城と言われていたその会社。世代交代し、「ホワイト企業になる」という新社長の方針の下、ここ数年、若手社員の残業は極力抑えられ、経営会議の主題の一つが有給休暇取得率となり、労働時間が長引きそうであれば、与える仕事を抑えることが当然のようになっていました。
しかし、仕事がなくなったわけではありません。そのしわ寄せは、長労働時間が染みついた管理者やベテラン社員が補うこと。
この結果、何が起こったか。
管理者やベテラン社員は、忙しいものの以前と同様に仕事の喜びを感じ、達成感を得ながら仕事をする。一方で若手社員は、仕事はしてはいけないもの、できなくても許されるものとの認識が生まれてしまったのではないか。
これはあくまでも私の推測に過ぎませんでしたが、社長自身、思い当たるところがあるようで、力なくうなだれるばかり。
そこで私は「社長の最大の仕事は、社員さんに仕事の喜びと働き甲斐を感じさせること」とお伝えし、改めて“働く”ということの意味を考え直していただくようにお願いしました。
新体制になって丸2年。「改革には同じだけの時間がかかることを覚悟してくださいね」と脅しつつ、その会社に必要と思われる改善策をいくつか提示させていただきました。
この会社に限らず、社員さんから「働くことは罪」と思われるような施策を、「環境適応だ」と思い込んで真剣に実施している会社が散見されます。
ぜひ皆さんの会社では、働くことが喜びとなるような『働き方改革』を実施していただきたいと思います。そのためにも今行っている施策を棚卸し、働く喜びに繋がるものになっているかどうかの再確認を行っていただければと思います。