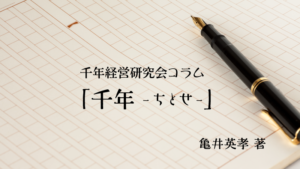No.770 評価
9月決算の当社では、現在『決算賞与』支給に向けた人事評価を実施しています。
人事評価の視点には二面性があります。
ひとつは『能力評価』で、事前に伝えた期待に対する実現度を評価するします。人によって期待は異なりますから、評価は他と比較することのない“絶対評価”となり、評価結果は専ら昇給および昇格に反映させます。当社の昇給・昇格は4月ですので、この能力評価は3月に行います。
もうひとつが『成果評価』で、一定期間の成果や取り組み状況などが評価の対象となります。これは他との比較が可能ですから“相対評価”となり、評価結果は専ら賞与に反映させます。今回の決算賞与に関わる評価は、まさにこの視点となります。
相対評価とはいうものの、新入社員とベテラン社員を同列で評価することはできませんから、同等の能力を保有する者をグルーピングする“等級分け”が必要です。
一般的には、部長・課長・係長・主任と言った役職区分に加え、一般社員の中でも何段階かに区分します。当社では13段階の等級がありますが、社員数によって適正な投球を設定します。細か過ぎると相対評価ができませんし、少な過ぎると適正な比較ができません。最低でもすべての等級で3人以上の者がいる状態を想定して区分していただくとよいでしょう。
適正な等級区分ができれば、等級ごとに期待成果を設定し、それぞれの達成度を比較検討しながら評価をしていくことになります。
人事評価の目的は、「期待人材像の明確化」「目標達成の促進」「適材適所の配置実現」「組織内コミュニケーションの充実」ですから、期待成果を事前に設定することが何より大切です。
そして、単に評価するだけでなく、その評価結果を『フィードバック』することによって、成長を促すことが重要です。評価後の個別面談はマストとお考え下さい。
その際、何よりも“納得感”を得ることが大切です。評価結果の説得力を高めるために、客観的事実の“見える化”を図ることを心掛けましょう。
ぜひ皆さんの会社でも、適正な評価を実施されることをおすすめします。当社の人事コンサルティング部門は間違いなく日本一の集団です。もし、具体的に検討されるのであれば、ぜひお声がけください。お待ちしています。