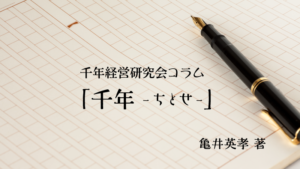No.768 現場
私が入会している倫理法人会の9月から始まる新年度において、『後継者倫理塾』という名の、後継者を対象とした研修の塾長を拝命しました。
正直なところ、独立開業という時期に、かつ私の人生のメインテーマともいえる内容の研修のお世話役という役割に、当初はお断りするつもりでした。しかし、愛知県の次期会長から直々に「県の標準を創って欲しい」と言われてしまい、お断りすることができませんでした。
また、標準つくりという方針もあってか、先代からの引き継ぎもままならず、ほぼゼロベースでの立ち上げとなりました。
いろいろな資料を紐解きながら、「①目的・スローガン・活動方針の決定」「②サポートメンバーの確定」「③研修内容の選定」「④プログラムの決定」「⑤募集業務の推進」「⑥派遣責任者および入塾希望者事前面談の実施」「⑦予算書作成」「⑧活動計画書の作成」などの活動を進めていく中で、最も苦労したのが⑤の募集活動でした。
塾長を引き受けたのが5月中旬で、募集体制が整ったのが6月中旬。10月開講ながら、8月20日には最少催行人数10名の募集を完了しなければなりません。何の伝手もない中で、募集期間はわずか2か月。当初は「何とかなるだろう」と安易に考えていたものの、時が流れていく中で、「これはちょっとやばいかも」と感じ始めました。
実際、8月1日の段階でまだ5名、途中夏期休業をはさみますから、実質10日ほどしかない中で、残り半分を集客しなければならない状況にありました。「ヒリヒリする」という感覚を初めて味わいました。
結果は、今日の段階で11名のお申込み。多くの方のご協力で、何とか開講することができる状況になりました。
今回改めて感じたのは、『現場主義』の大切さです。当初は、②で選定したサポートメンバーと共に、県内に31か所ある単会という支部組織の会長からの声掛けを依頼するという形式をとっていました。しかし、なかなか候補者を発掘することができず、まさに「居ても立ってもいられず」に各単会に足を運ぶようになりました。その結果、それまで「うちには候補者はいません」との回答だった単会からも、どんどん候補者が出てくるようになりました。
行ってみてわかったのは、お配りしたチラシが会長の車の中に隠匿されていたり、中には「後継者倫理塾って、どんな研修でしたっけ?」という会長もいらっしゃったこと。人伝のお願いの虚しさをつくづく感じることができました。
もちろん、事がうまく回っているようであれば、トップが現場に足を運ぶ必要なないのかもしれません。しかし、結果が出ない、ないしは現場の状況がつかめない場合は、『現場主義』に立ち返らなければいけない、そのことを改めて学ばせていただきました。
おかげさまで、来期は29名の候補者を擁して募集活動を行うことができる状況にあります。また、それに甘えることなく、できるだけ早い時期に現場を回り、今以上の候補者を掘り起こしつつ、募集活動においても永続的な愛知県標準の確立をしていきたいと思います。