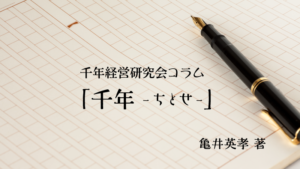No.767 歴史
先日、ある会社の新任管理者研修の講師を務めてきました。
その会社とのお付き合いが始まったのは今から27年ほど前、現社長就任のおよそ1年前のことでした。バブル崩壊の傷跡深く、企業再生のお手伝いに入らせていただくことになったのがきっかけです。
社長は次男で、継ぐどころか、会社に入る予定もありませんでした。しかし、後継予定だった兄が退社したことから白羽の矢が立ち、32歳で入社されました。しかしそれは、まさにいばらの道への入口でした。
彼が入社したのは1995(平成7)年、バブル崩壊の荒波が東海地方にも襲い掛かり始めたころ。そして社長になった1999(平成11)年は、会社存続のオールを金融機関に握られそうになっていた時期でした。実は、入社わずか4年での社長交代もその流れの中にありました。
大変厳しい舵取りでしたが、あらゆる手段を行使し、何とか利益を計上できるまでになり、2008年には過去最高の売上高を計上するまでになりました。ところが、安堵したのも束の間、翌年にはリーマンショックの影響で売上は4割減。また存続の危機に晒されることになりました。
しかし、「二度と社員を辞めさせない」と心に決め、社員総動員であらゆる経費をカット。給与・賞与は減額したものの、一人の退職者も出さずに利益を出すことができました。「初めて自分自身に自信が持てた。そして周囲からも初めて社長として認めてもらえたと思う」との言葉が忘れられません。
今回の受講生は、バブル崩壊もリーマンショックも知らない世代。そこで、今回の研修では、最初の1時間、社長に講話をいただきました。
講話終了後の休憩時間には、「話には聴いていたが、それほどまでとは知らなかった」「社長が厳しいことを言う意味が初めてわかった」など声が聴こえ、その後の研修も、心地よい緊張感の中で進めることができました。
今回、改めて思ったのは、会社の歴史を共有する価値です。後継者を含め、途中から入ってくる社員は、山登りで言えば途中からヘリコプターで舞い降りてくるようなもの。それまでの苦労を知らずに入って来て、やれこれが足りない、やれこれがダメだなどと、不足することばかりに目が行くもの。
しかし、それまでに多くの問題を解決してきたからこそ今がある。まずはそのことを知る必要があると思うのです。その上で、そこからの学びや気づきを共有する。そのような取り組みが大切なのです。
また、お話の中で「祖父が作ってくれた会社、親父がつないできてくれた会社、みんなが頑張って残してきてくれた会社。やれる自信はなかったが、継がないという選択肢はなかった」との言葉が印象的でした。後継者のあるべき姿勢の表れだと思います。
いずれにしろ、会社の歴史を残し、伝えていくことは、企業経営にとってとても大切なことです。皆さんもこれを機に、自社の歴史をきちんと言葉に残す取り組みをしていただければと思います。