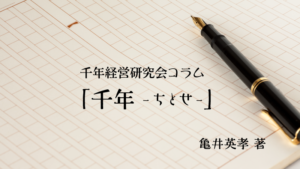No.764 資金
このところ、資金繰りが厳しくなってきている企業が多くなっているようです。
先日も、ある社長から相談を受けました。その会社、以前はとても儲かっていたので内部留保は潤沢、自己資本比率も70%を超えているにも関わらず、お金がない。
皆さんも一度やっていただきたいことがあります。直近2期分の決算書を用意し、貸借対照表の2期比較をして、その増減額を算出してください。
まず、「純資産の部」の増減を見ます。すべて現金取引をしていれば、原則としてその増減額は、「現預金」の増減額と一致するはずです。
ところが、今回の会社もそうでしたが、純資産の部の減少額(赤字の額)よりも、現預金がかなり大きく減少していました。要するに、他の財産に資金が流れていることを意味します。
そこで、増減している財産を見てみると、この会社の場合、大きな動きとしては
- 保険積立金:増
- 長期借入金:減
- 役員借入金:増
という結果になっていました。
要するに、現預金の減少の原因は、①保険積立金の積み増しと、②長期借入金の返済であり、それでも足りないので③役員借入金を増やしている、という状況であるということです。利益が出ていない今のままでは、資金の不足を役員借入で補い続けるという構図から抜け出すことができません。
そのためにも、まずは保険の積み立てを止める必要があります。積み立てを止めれば、損益計算書上の「保険金」も減少し、利益にも貢献します。
ところが、そのことをお伝えすると、「付き合いでなかなか止められなくって」との回答。先代までが積み上げてくださった内部留保の上に胡坐をかいてきた後継者にありがちな甘え、厳しくご指導させていただきました。
そして何より、利益を出すことが必要です。長期借入金の返済額は、税引後利益で補う必要があります。その点もお伝えした上で、収益改善のポイントをご指導させていただきました。
いずれにしろ、自社における資金の流れをきちんと把握しておくことが大切です。ぜひ貸借対照表の2期比較、実施していただければと思います。